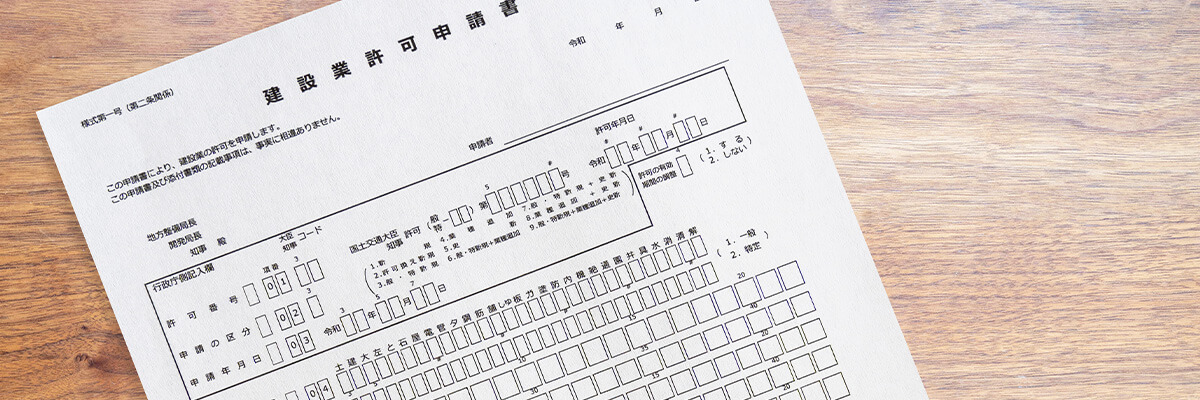
新規での建設業許可の手続き、お困りではありませんか
建設業許可を取って金額の大きな仕事を請け負いたいとお考えの皆様におかれましては、私の経験上、次のようなお悩みや疑問をお持ちではないかと想像します。
- 自社が現在、建設業許可をとれる状況なのかどうかが分からない
- 工事現場での仕事が忙しく、役所に行ったり、書類をつくったりする時間がない
- 元請から急いで建設業許可を取るようにと言われている
- 一度役所に相談に行ったが、何を言っているのか分からなかった
- 社長に建設業の経営経験がない場合や資格者がいない場合、許可は取れるの?
建設業許可を取ろうと考えている皆様は、すでに周りの許可業者に相談してみたり、インターネットで情報を収集したりされていると思います。おそらく、ネット上には許可を取るための要件が詳しく書いてあるでしょう。
しかし、許可の要件がどういうものなのかを理解することも大事ですが、それよりも重要なことは皆様の会社が許可の要件を満たしているのかということではないでしょうか。また、要件を満たすことを示すための書類の選択も、建設業許可の申請を行う上ではかなり重要です。
決して簡単ではない建設業許可の手続き
ところで、建設業許可を取得するためには、都道府県が示している「手引き」などをもとに、自社が許可をとれる状況なのかを確認し、必要とされる書類を収集し、さらに法令で定められた様式の申請書を作成するというプロセスを踏むことになります。
しかしながら、そもそも許可の要件が分からなければ先へは進めませんし、許可の要件を満たしているかの判断をするためには、相当の勉強をしなくてはなりません。場合によっては平日に何度も役所に相談に行く必要が生じることもあります。いずれにしましても、大変な手間がかかるでしょう。
当事務所にご相談をいただくケースでも、「許可をとれるかどうか確認して欲しい」というものが最も多く、「手続きを進める時間がないので代わりにお願いしたい」というものがこれに続きます。専門の事務職員がいらっしゃる会社から、「自社で役所に聞きながら進めようと試みたが難しかった」ということで、ご依頼があったケースもあります。
皆様がご苦労されている建設業許可の取得ですが、いったいどのような要件をクリアすればよいのでしょうか。また、許可取得までの手続きはどう進めればよいのでしょうか。
建設業許可を取得するための要件を簡単に解説
ここでは、新規に建設業許可を取りたいとお考えの皆様へ、許可の要件をごく簡単に解説します。許可を審査する役所はどのようなことを確認するかを事前に知っておきましょう。なお、以下の要件をクリアしているかどうかは、申請する側が書類によって証明することになります。
- 欠格要件に該当していないこと
- 常勤の役員(事業主)の中に建設業の経営業務についての責任者がいること
- 営業所に常勤する技術者(専任技術者)がいること
- 営業所の実態があること
- 十分な資金があること
- 社会保険にきちんと加入していること
建設業許可を取得できるかどうかは、上記の許可の要件を満たしていることを書類で証明できるかがポイントとなります。そして、この証明こそが最も難しいものであると私は考えています。
建設業許可の手続きの流れ
続きまして、新規で建設業許可を取得するまでの大まかな流れを示します。建設業許可取得までのプロセスは、①申請書類を整えて役所に提出するまでと、②役所が審査して許可証が発行されるまでの2段階に大別できます。
②の期間については申請者側でコントロールできるものではありませんが、①の期間については建設業許可を得意とする行政書士に依頼することによって、大幅に短縮できるものと思われます。
- 自社(自己)が建設業許可の要件を満たしているのかを確認する。
- 都道府県の「手引き」で示されている証明書類を揃えることができるのかを確認する。
(必要に応じて役所の担当者に照会を行う)
- 建設業許可の申請書類を作成し、役所に提出する。
- 都道府県または国土交通省の審査を受ける。
- 建設業許可証の交付を受ける。
なお、建設業許可の審査は通常1ヵ月程度(国土交通大臣許可の場合は2~3カ月程度)かかります。この期間については大きく短縮されることはありません。
行政書士佐藤勇太事務所の建設業許可、解決事例
当事務所では、主に福島県内の建設業者様のご依頼を受け、様々なケースの建設業許可申請を経験してまいりました。ここでは、いくつかの事例についてご紹介したいと思います。
解決事例1 「定款作成が必要となったケース」
有限会社として、長い間建設業許可業者だったこの会社は、5年ごとの更新の手続きを失念してしまい、新規の建設業許可が必要になりました。新規での建設業許可の申請では、添付書類として会社の定款(写し)を提出する必要があります。
しかしながら、事務所のどこを探しても定款が見当たりません。また、法務局の保管期間が切れてしまっているため、定款が提出できないという事態に陥ってしまいました。そこで、当事務所が現在の会社法に合わせて定款を再作成し、これを添付することで許可を取ることができました。
解決事例2 「確定申告書を修正していただいたケース」
個人事業主が「法人成り」した場合、経営業務の管理責任者の要件を満たしているかどうかは、個人事業主の期間と会社の役員としての期間を合算することができます。そして、個人事業主としての期間は所得税の確定申告書によって証明することになります。
確定申告書の審査では、事業主の職種の欄がポイントとなります。職種の内容から建設業を営んでいることが読み取れない場合には、建設業の経営経験があるとみなされません。このケースではどういうわけかこの欄が空欄でした。請求書などで工事実績を示しても県は認めてくれません。
やむを得ず、税務署の担当者の許可を得て、この欄に「土木工事業」を書き加え、無事に許可を取ることができました。税務署でも過去にさかのぼって修正を認めるのは例外とのことでした。
解決事例3「営業所の専任技術者を10年の実務経験で証明したケース」
営業所ごとに配置しなければならない専任技術者ですが、建設業法で定められた資格を持っている者がいればその証明は決して難しくありません。しかし、実務経験のみで専任技術者の要件をクリアしようとする場合、10年間の経験の積み重ねが必要です。
福島県においては、実務経験を「請求書等+通帳への入金記録」で証明しようとすると、1か月に1枚の請求書等が必要となります。つまり、120か月分の書類の確認作業が必要となることになります。前に勤務していた会社から書類を借りなければならないこともあります。
資格者がいないからとあきらめている事業者様についても、書類が残ってさえいれば許可の可能性はあります。当事務所ではこのような難しい案件についても果敢にチャレンジしています。
建設業許可申請のこと、当事務所に相談してみませんか
さて、自社で建設業許可の申請をしようとすると、許可が取れる状態なのか分からないとか、許可を取るまでの時間を短縮したいといった場面に直面することも多いのではないでしょうか。
当事務所では、建設業許可を取得して事業を成長させたいとお考えの皆様に対し、建設業許可の申請手続きを代行するサービスを提供しております。ご依頼をいただきますと、役所に問い合わせをしたり、申請書類を作成したりする手間を大幅に省くことができます。
当事務所では、建設業者様に対し、事業を成長させるためのハードルである建設業許可の手続きをできるだけ苦労なく乗り越え、本業である工事の施工等に集中していただきたいと考えています。手続きを専門家に依頼したい、外注したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所の建設業許可代行サービスを利用するメリット(当事務所の強み)
以下では、行政書士佐藤勇太事務所に建設業許可の手続きを依頼するメリットについて述べたいと思います。どの行政書士事務所に依頼するかを選定する際の参考にしていただければ幸いです。
建設業許可に精通している行政書士がすべて責任をもって対応
当事務所は、代表者である私がすべての業務を担当しています。貴社が許可の要件を満たしているかの調査、役所への照会、書類の作成・提出まで責任をもって対応しております。もちろん、受注できる件数は限られていますが、その代わり「かゆい所に手が届く」事務所であると自負しています。
業務を依頼された場合には、こちらからも逐次進捗状況をお伝えしますが、代表者直通の携帯電話番号をご担当者様にお伝えし、いつでも連絡がとれる体制をとっています。貴社の状況に合わせて柔軟な対応が可能であることは当事務所の強みといえます。
業種追加、経営事項審査や入札参加資格申請にも対応
当事務所はレディメイド(既製品)を提供する行政書士事務所ではなく、オーダーメイドのサービスを提供する事務所です。建設業の手続きについても、新規の建設業許可だけを大量に受注するという考え方はとっていません。
ご存じのとおり、事業の規模が大きくなれば、許可の対象となる業種を増やしたり、一般建設業から特定建設業の許可に切り替えたり、公共工事の入札に参加したりといった別な手続きが発生することになります。当事務所では、許可後のサポートについてもお客様の状況に合わせて対応しています。
産廃の収集運搬、農地転用などの関連する手続きの実績も多数
建設工事現場から排出される廃棄物を、元請から委託を受けて中間処分場に運搬するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。また、住宅を建築する場合や資材置場を設置する場合には、農地転用や開発許可といった土地利用に関する手続きが必要となります。
当事務所はこれらの手続きについての実績も多いため、お客様の多様なニーズにお応えできるものと考えています。建設業に関する手続きと土地利用に関する手続きの2つの分野に精通している行政書士事務所は、数少ないものと認識しております。
当事務所が提供する建設業許可代行サービスとは
ここでは、当事務所が提供する建設業許可代行サービスの内容や料金、対応エリアについてご案内します。
建設業許可代行サービスに含まれるもの
- お客様との事前相談
最初の打ち合わせでヒアリングと書類の確認をさせていただき、許可の可能性があるかどうかを検討します。 - 申請手続きに必要な書類の収集
許可の要件を満たしていることを証明するための書類を収集します。必要に応じて役所の担当者と連絡をとり、協議を行います。 - 申請書類の作成・窓口への提出
法令で求められている様式に従い申請書を作成し、収集した書類を添付して、役所の担当窓口に提出します。 - 補正指示への対応、許可証の受け取り
書類を受領した役所から問い合わせがあった場合の対応、追加書類の提出が必要になった場合等の対応を行います。
建設業許可代行サービスの料金(知事許可のケース)
以下では、よくあるケースについての標準的な料金についてお示しします。お見積りについては、初回相談・調査が終わった段階で正確にご提示しています。
調査業務
資料の確認に多くの時間を要する場合や許可行政庁との事前協議が必要な場合には、調査料をいただくことがあります。調査料が発生する際には、事前に正確な料金をご提示いたします。
| ケース | 標準報酬額(税込) |
|---|---|
| 調査が必要な場合 | 22,000円 |
書類作成・申請代行業務
申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成の上、担当窓口に提出します。その後の対応についても責任をもって対応します。
お支払いについては、契約締結時に着手金として法定手数料を含めた料金の50%を頂戴いたします。その後、申請が受け付けられた際に残金と諸経費(証明書交付手数料など)を請求させていただきます。現金または振り込みでのご対応をお願いします。
| ケース | 標準報酬額(税込) | 申請手数料(証紙代) |
|---|---|---|
| ・経管が建設業許可業者での役員経験(5年以上)あり ・営業所技術者が国家資格等を保有 |
121,000円 | 90,000円 |
| ・経管が建設業許可業者以外の会社で役員経験(5年以上)あり ・営業所技術者が国家資格等を保有 |
154,000円 | 90,000円 |
| ・経管が建設業許可業者以外の会社で役員経験(5年以上)あり ・営業所技術者の要件を実務経験で自己証明 |
198,000円 | 90,000円 |
サービス提供が可能な地域
福島県中通り地域の市町村
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、三春町、鏡石町、矢吹町、泉崎村
その他福島県全域を対象エリアとしています。
県外の建設業者様については、オンライン対応・オンライン申請でよろしければ対応させていただきます。
建設業許可代行サービス、ご依頼までの流れ
-
お問い合わせ
メール、またはお電話にてお問い合わせください。簡単なご質問をさせていただき、許可の見込みがまったくない場合にはこの時点でお伝えいたします。許可の可能性がある場合には、初回面談の日時・場所などについて調整させていただきます。なお、問い合わせの電話は20分までとさせていただいております。
-
初回相談
当事務所またはお客様ご指定の場所にて、会社の状況についてヒアリングを実施し、書類を確認させていただきます(Zoomでの対応も可)。許可の可能性があると判断した場合には、お見積りを提示いたします。
また、残念ながら現時点では許可を取れないと判断した場合には、どうすれば許可が取れるのかについてご提案いたします。
-
ご依頼・ご契約
サービス内容・見積額にご納得いただけた場合には契約書を取り交わします。Adobeでの電子契約も可能ですのでご検討ください。契約を締結しましたら申請手数料をお預かりし、その後に業務に着手いたします。
建設業許可申請のよくあるご質問
建設業許可を取得したい方へ、行政書士からのメッセージ
建設業はインフラを整備し、私たちの日常生活を支えている重要な産業です。また、災害時においては、地元での復旧活動にあたるなど、社会に多大なる貢献をしています。
建設業許可の取得は、重要な存在である建設業者様が事業を成長させるための最初のハードルといえます。私は、建設業許可の代行業務を迅速かつ適正に行い、皆様のご期待に応えていきたいと考えています。


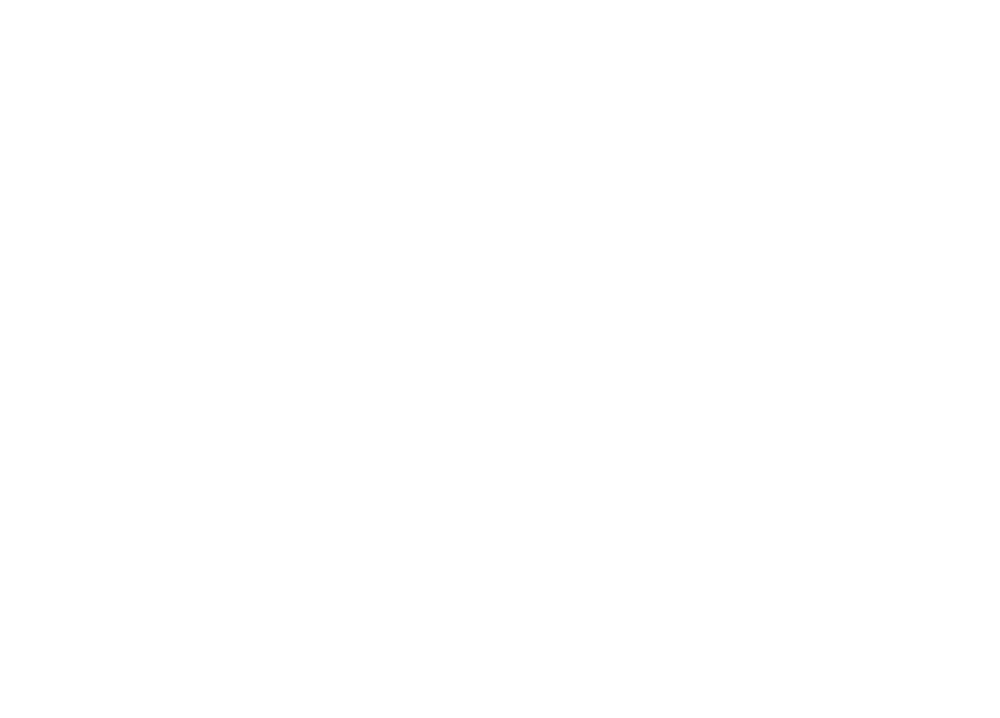


 事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。 行政書士 佐藤勇太
行政書士 佐藤勇太