
建設業界で事業を展開されている皆様にとって、経営事項審査は公共工事の受注や取引先との信頼構築に欠かせない重要なプロセスです。経審では、会社の財務状況や技術力、工事実績など多岐にわたる項目が評価されますが、その手続きや必要書類の準備は複雑で時間もかかります。
当事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、書類作成から申請手続き、さらには審査後のフォローアップまで一貫してサポートしています。皆様が安心して審査に臨み、公共工事の受注や新たな契約獲得に繋げられるよう、最適なアドバイスとサポートを行います。事業の成長と安定を目指す皆様のパートナーとして、ぜひ当事務所をご活用ください。
経営事項審査、こんなお困りごとはありませんか
ところで、皆様が経営事項審査を受ける際に感じる「困りごと」には次のようなものがあるのではないでしょうか。
- 必要とされる書類が多く、何を準備したらよいか分からない
- 評価基準が難しく、どうしたら点数が上がるのか分からない
- スケジュール管理が難しく、すべて専門家に任せたい
- 電子申請が増えているが、対応するのが難しい
- 法令の改正が度々あり、情報を追いかけるのが大変
また、経審は最終的な評価(P点)を受けるまでのスケジュール管理がとても重要です。締切日までに審査を終えていないと公共工事への入札ができなくなる期間が生じます。重大な損失となりますので注意が必要です。
経営事項審査とはどのような制度なのか
ご存じのとおり、経営事項審査は、建設業者が公共工事を受注する際に必要となる審査です。会社の経営状況、技術力、財務状況などが総合的に評価され、点数がつけられます。この点数は、公共工事の入札参加資格や落札の可能性に影響します。
経審の成績が良い会社ほど、より大きな規模の公共工事を請け負うチャンスが広がります。これは、経審の結果が会社の信頼度を示す指標となり、発注者が安心して工事を任せられる会社かどうかを判断する材料となるためです。つまり、経審は建設業者様にとって、公共工事を受注するための重要な「登竜門」と言えるでしょう。
また、経審は、業者を選別するだけでなく、会社が自らの経営を見直し、改善する機会を与える役割もあります。このプロセスを通じて、建設業界全体の質の向上が期待されます。そこで、まずは自社の経営状況や技術力を客観的に見つめ、審査に備えることが重要です。
経営事項審査の手続きの流れ
ところで、経営事項審査を受けるためにはどのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。ここでは一連の手続きの流れについて簡単に解説します。
1.決算変更届の提出
毎事業年度終了後、決算日から4か月以内に管轄の建設事務所へ決算変更届を提出します。必要書類には建設業財務諸表や事業税納税証明書などが含まれます。これにより、財務状況の最新情報を登録します。
2.経営状況分析申請
決算変更届の提出後、経営状況分析機関に対して、経営状況分析申請を行います。分析申請書を作成し、決算書などの関連資料を添付して提出します。これにより、財務状況の評価が行われます。この手続きについては、電子申請が主流となっています。
3.経営状況分析結果の受領
経営状況分析機関から分析結果を受け取ります。これにより、財務面での客観的な評価を確認できます。
4.経営規模等評価の申請
経営状況分析結果を踏まえ、県に経営規模等評価と総合評定値の請求申請を行います。工事経歴書や技術力(Z点)評価資料、社会性(W点)の評価資料などを準備して提出します。
5.審査と評価の完了
提出された各種資料をもとに、経営規模、技術力、社会性等の評価が行われ、審査が完了します。その結果として、総合評定値(P点)が決定されます。
6.評定値通知書の受領
審査の完了後、総合評定値通知書が交付されます。得られた評定値(P点)は、公共工事の入札参加資格審査などで活用されることになります。
経営事項審査を行政書士に依頼するメリット
経営事項審査の手続きは、建設業者様にとって非常に重要である一方、専門的な知識が求められるため、準備や手続きには多くの時間と労力がかかります。このような課題を解決するためには、行政書士に依頼することが最適な選択肢となります。そのメリットをさらに詳しくご紹介します。
時間と労力の節約
経審は、決算書や工事経歴書、技術者の情報など、多くの書類を正確に準備する必要があります。これに加え、提出期限や評価基準を正確に把握する必要があり、業務との両立は簡単ではありません。行政書士に依頼することで、これらの負担を軽減し、安心して本業に集中できます。
申請の正確性向上
経審に関する法令やガイドラインは頻繁に改正されます。そのため、最新の基準に基づいた申請を行うためには専門的な知識が必要です。行政書士は常に最新の情報を把握し、正確な書類作成を行います。これにより、手続きミスや不要なトラブルを回避できます。
点数アップへの具体的アドバイス
評価基準は複雑であり、点数を最大化するための方法を独自に見つけるのは困難です。行政書士は、お客様の会社にとって最適な改善策を提案し、技術者情報や社会性に関する事項を適切に整理することで、総合評定値(P点)の向上をサポートします。
電子申請への完全対応
最近では経営状況分析申請をはじめとする多くの手続きが電子申請化されています。これに対応するには、専用システムの操作やデータ形式への対応が求められます。行政書士に依頼することで、これらの煩雑な手続きもスムーズに進めることが可能です。
安心のフォローアップ体制
経審は1回の手続きで終わるものではなく、毎年の更新や点数の見直しが必要です。当事務所では、審査後も長期的な視点でお客様の成長をサポートし、次回以降の審査への準備やアドバイスを継続して提供いたします。
当事務所に依頼する理由
行政書士佐藤勇太事務所では、建設業者様に特化したサービスを展開し、多くのお客様から高い評価をいただいております。ここでは、当事務所が他の事務所と一線を画すポイントをご紹介します。
個別対応で安心サポート
お客様ごとに異なる事業規模や経営状況に応じた、オーダーメイドのサービスを提供します。初回のご相談から最終的な手続き完了まで、一貫して丁寧な対応を心掛けています。特に初めて経審を受ける方や、過去に失敗した経験のある方もご安心ください。
スピード感と柔軟性
締切間近のケースにも迅速に対応し、必要書類の準備から提出までスムーズに進めます。また、予期せぬトラブルが発生した場合でも、柔軟に対応できる体制を整えています。
最新情報の提供
経審に関する法改正や新たな制度変更に迅速に対応し、お客様に必要な情報をタイムリーに提供します。これにより、事業活動に支障をきたすことなく手続きを進めることができます。
ご依頼・手続き完了までの流れ
それでは、経営事項審査(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得)の申請代行を当事務所に依頼する場合の流れについてご説明します。
Step1 お問い合わせ
ホームページの「お問い合わせフォーム」またはお電話でご連絡ください。ご相談内容を簡単にお伺いし、初回相談の日程調整を行います。
Step2 初回相談・ヒアリング
初回相談にて、貴社の経営実態や審査に関するご希望を詳しくヒアリングします。必要な手続きやスケジュールについてご説明いたします。初回の相談料は無料です。
Step3 お見積りとご契約
ヒアリング内容をもとに、必要なサポート範囲と料金をお見積もりします。サービス内容をご確認いただき、ご納得いただいた上でのご契約となります。
Step4 書類準備と作成
経審に必要な書類を整理し、当事務所が申請書類を作成します。お客様と密に連携し、正確かつ迅速に書類を整えます。
Step5 申請・フォローアップ
作成した申請書類を速やかに行政機関に提出し、審査が問題なく進行するようフォローします。必要に応じて追加資料の準備や対応を行います。
Step6 結果報告と次ステップのご提案
経審の結果を受け取り次第、お客様にご報告します。必要に応じて、次回の改善案や経営戦略に関するアドバイスもご提供します。
業務と料金、対象エリア
行政書士佐藤勇太事務所が提供するサービスと料金、そして業務対応が可能な地域についてご案内します。なお、表示されている料金は、おおよその概算です。より正確な金額については、契約の前にお見積書を作成してご確認いただきますのでご安心ください。
決算変更届
| 標準報酬額(税込) | 納税証明書取得手数料 |
|---|---|
| 39,600円 | 1,100円 |
経営状況分析申請
| 標準報酬額(税込) | 申請手数料 |
|---|---|
| 22,000円 | 13,800円 |
経営事項審査申請
| 標準報酬額(税込) | 申請手数料 |
|---|---|
| 77,000円 | 1業種11,000円~ |
サービス対応エリア
福島県中通り地域の市町村
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、三春町、鏡石町、矢吹町、泉崎村
その他福島県全域を対象エリアとしています。
地域のインフラを支える建設業者様へ
当事務所は、地域のインフラを支える建設業者の皆様が、円滑に経営事項審査をクリアし、地域社会に貢献し続けられるよう全力でサポートいたします。
建設業者様が手掛ける公共工事は、道路や橋、水道、学校といった地域住民の生活を支える基盤となるものです。その重要性を深く理解しているからこそ、私たちお客様の成長と成功に寄り添い、専門的な知識と経験を最大限に活かして支援しています。
経審を通じて、建設業者様が得た信頼は、地域社会全体に安心を与え、さらに発展的な未来を築く力となります。当事務所では、単なる書類作成に留まらず、「地域の未来を共に創る」という思いを持ってサポートさせていただきます。
ご相談・お問い合わせはこちらから
公共工事への参加を目指す建設業者様にとって、経営事項審査は事業成長の鍵となる重要なプロセスです。しかし、その手続きや評価基準を正確に理解し、確実に進めるためには専門家のサポートが必要不可欠です。
当事務所では、お客様一人ひとりの目標達成を全力でサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


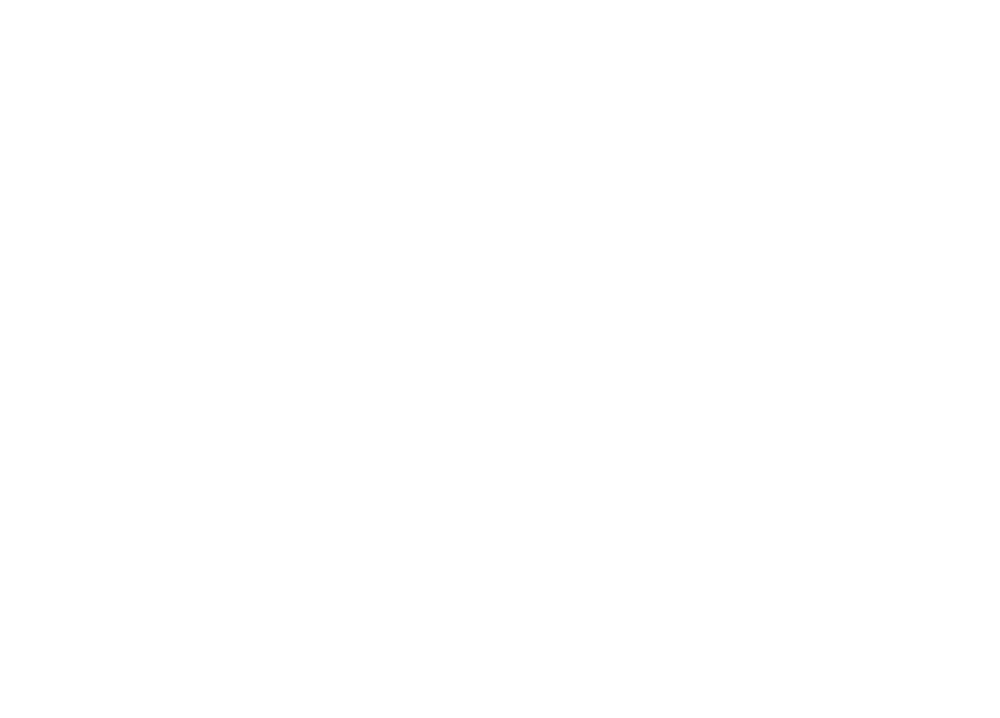


 事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。 行政書士 佐藤勇太
行政書士 佐藤勇太