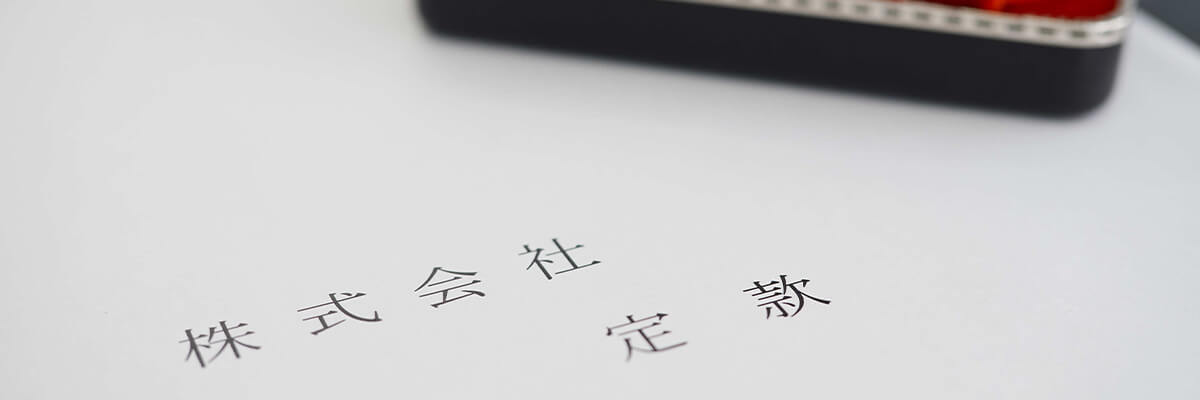
事業の規模を拡大し、建設工事で利益を上げていくためには、信用を高め、金額の大きな工事を請け負っていくことが重要です。そして、そのためには、会社をつくって法人化し、建設業許可を取得することが最適なルートとなります。
ところで、現在、個人事業として建設工事を請け負っている皆様の中には、以下のような疑問やお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 会社設立の手続きの流れが分からず、何から手を付けたらよいのか困っている
- 会社設立と同時に建設業許可も取得したいと考えているが、誰に相談すればよいのか分からない
- 現在持っている建設業許可を、法人成りした後も引き継ぐことができるのか教えて欲しい
- 会社設立の手続きは専門家に任せて、自分は現場での施工に集中したい
個人事業主の場合、事業主様ご自身がすべての業務を担っていることも多く、複雑で面倒な書類作成や行政手続きに時間と労力を割くことが難しいケースも多いことでしょう。上記のような困りごとがある方は、どうぞ当事務所までご相談ください。
建設業での会社設立は建設業許可の知識が不可欠
会社を設立し、法人化することは、取引先や金融機関からの信用を高めることにつながります。また、金額の大きな工事や公共工事の受注にも貢献するものと思われます。しかしながら、会社設立の手続きは、なかなか複雑で手間のかかる作業です。
建設業で会社を設立するためには、会社の基本事項を決定し、定款を作成して公証人の認証を受けた後、法務局に会社設立の登記申請をすることが必要です。言葉にすればたったこれだけのことですが、実際には専門家の支援がなければかなり難しい手続きです。
特に建設業での会社設立は、建設業許可との関連を考慮しながら手続きを進めなければならないため、より注意深い対応が必要とされます。「せっかく会社ができたのにそのままでは許可が取れない」といった事態は避けなければなりません。
当事務所にご相談をいただくケースでも、「資本金の額をどのように設定したらよいか分からない」とか、「定款の事業目的の適切な書き方を教えて欲しい」とか、建設業許可の取得や維持に関係するものがあります。
しかしながら、こういった質問をされるのはある程度知識がある方であり、こちらから情報を提供しないと気がつかない方も一定数いらっしゃいます。つまり、建設業法や建設業許可制度に対する知識がないと、会社設立の目的が達成されないというリスクがあるわけです。
こうしたリスクを避けるためには、まずは、建設業許可申請や入札参加申請などの建設業に関係する業務に精通している行政書士に相談するのが最善の選択肢なのではないかと思います。いかがでしょうか。
また、すでに建設業許可を持っている個人事業主が法人成りする場合には、さらにきめ細かい配慮が必要になります。個人から法人への許可の引き継ぎは、準備しなければならない書類も多く、行政(役所)との綿密な打ち合わせが求められることになります。
建設業での会社設立、手続きの流れを簡単に解説
さて、個人で建設業を営んでいる方が、会社を設立し、建設業許可を取得するためには、いったいどのような書類をつくり、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。以下では、株式会社を設立することを前提としてごく簡単に解説しています。
①会社の基本事項を決める
商号(会社名)、本店の所在地、資本金の額、役員構成、事業目的を決定します。ここで最も注意を要するのが会社の事業目的です。建設業には29の業種がありますが、建設業許可を取りたい業種が事業目的に入っていることが重要です。また、商号が決まったら、会社の実印を作成しておきます。
②定款を作成し、公証人の認証を受ける
会社の基本的なルールを定めた文書である「定款」を作成し、公証役場にて認証を受けます。株式会社のような法人は、定款で定めた事業目的に沿った活動しかできません。そのため、今後の事業の成長・拡大を見通した事業目的を設定する必要があります。
例えば、不動産業(宅地建物取引業)や産業廃棄物収集運搬業に進出する可能性があるのであれば、予め定款に記載しておく方がよいでしょう。これらに限らず、行政の許認可が必要な事業を実施する場合には、事業目的の文言にまで注意を払う必要があります。
③法人の設立登記を行う
定款を作成し、公証人の認証を受けた後は、資本金の払い込みを行い、法務局に対して設立登記の申請をします。ただし、登記申請を行政書士が行うことはできませんので、司法書士に委任することになります。なお、当事務所ではお客様の利便性を鑑み、司法書士の先生と提携し、ワンストップサービスを提供しています。
④税務関係・社会保険関係の届出をおこなう
会社が設立されましたら、税務署や都道府県税事務所に法人設立届出書を提出します。また、健康保険組合や年金事務所、労働基準監督署に対しても所定の届出を行うことになります。
建設業許可の新規許可申請、許可の引き継ぎについて
会社設立と建設業許可を同時に行う場合に、先に進めておかなければならないのは会社設立です。個人事業主として取得した建設業許可は、自動的には法人成りした後の会社には引き継がれないからです。順番としては、会社設立登記が完了したあとに許可申請を行うということになります。
建設業許可を新規で取得するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 経営業務の管理責任体制が構築してあること
- 営業所ごとに専任の技術者が配置されていること
- 財産的基礎や金銭的信用があること
- 営業所の実態があること
- 欠格要件に該当していないこと
- 適切な社会保険に加入していること
- 建設工事の請負契約に関して誠実性を有していること
ところで、③の財産的基礎ですが、一般建設業許可の場合、自己資本額が500万円以上あることが求められています。自己資本の額=資本金ではありませんが、会社設立後すぐに許可申請を行う場合、500万円の資本金があれば、要件をクリアすることになります。
次に、個人事業主から法人成りした後の会社に許可を引き継がせる方法としては、事前に行政と相談しながら、事業譲渡契約書などの書類を整え、法人成りの認可を受ける方法と、新たに法人としての許可を取得して、個人としての建設業許可を廃業する方法とがあります。
どちらの方法をとればスムーズに引き継ぎが行われるかは、事業者によって事情が異なります。メリットとデメリットを比較し、より適した方法で手続きを進めていくことが重要です。
建設業での会社設立、当事務所に相談してみませんか
会社設立や新規での建設業許可、建設業許可の法人成り認可の手続きをご自身で進めようとしても、書類の作成が難しいとか、時間が圧倒的に足りないとか、困難を抱えている状況が多いのではないでしょうか。
当事務所では以下の手続きに関するサポート業務を提供中です。
- 会社設立+法人での建設業許可申請
- 会社設立+建設業許可の法人成り認可申請
ご依頼いただけますと煩わしい書類作成や役所の担当者との協議から解放され、ご自身の「本業」に時間と労力を傾けることが可能です。また、専門家に依頼することで、目的に叶った会社を、早期につくることが可能になります。
会社設立や法人成りに伴う許可の引き継ぎでお困りの方は、一度当事務所にご相談ください。お客様の状況とご希望をしっかりと伺ったうえで、最適なご提案をさせていただきたいと考えております。
当事務所に建設業の会社設立を依頼するメリット
以下では、行政書士佐藤勇太事務所に会社設立などの業務を依頼するメリット、当事務所の強みについて述べたいと思います。相談先・依頼先を選定する際の参考にしていただければ幸いです。
建設業許可の取得を前提とした最適な会社が設計できる
建設業で会社を設立する場合、会社の形態、資本金、役員構成、事業目的などが建設業許可の要件を満たすように設計されていることが重要です。建設業許可に詳しくない専門家に会社設立を依頼すると、その後許可が取れない事態になり、会社の定款変更や役員変更が必要になってしまうリスクがあります。
当事務所では、建設業許可の新規取得、更新、業種追加の実績を積み重ねております。そのため、お客様の会社の将来を見据えた制度設計をご提案できるのではないかと思います。
許可取得までのスケジュール管理がスムーズ
会社設立と建設業許可の申請は、それぞれ手続きは異なりますので、別々の専門家に依頼することも可能です。しかし、当事務所にご相談いただければ、一連の流れを効率的に進められるスケジュールをご提案できます。
会社設立の登記は司法書士の先生にお願いすることになりますが、窓口を当事務所に一本化することが可能です。また、当事務所では、会社設立後すぐに建設業許可の申請ができるように書類を準備して、最短のルートで許可の取得を目指します。
会社設立後の建設業に関する各種手続きもワンストップ対応
建設業を経営していく過程では、建設業許可取得後も、以下のような手続きが必要になるケースがあります。
- 事業年度終了届(決算変更届)
- 業種追加や役員変更などの許可変更手続き
- 経営事項審査・入札参加資格申請
- 補助金申請
当事務所に会社設立などの業務をご依頼いただければ、お客様のスムーズな事業経営のために、建設業許可取得後の手続きも含めてサポートさせていただきます。許可の維持管理に関するご案内もいたしますので、「うっかり更新を忘れて許可が失効する」といったリスクを避けることができます。
当事務所の会社設立、建設業許可の法人成り認可申請サービス
ここでは、当事務所が提供している建設業での会社設立、建設業許可の法人成り認可申請について、内容や料金、対応エリアについてご案内いたします。
建設業の会社設立+建設業許可取得パック
建設業許可を持っていない個人事業主のお客様に対して、会社設立と新規の建設業許可申請をセットでお受けしています。この業務については、次のようなステップを踏んで手続きを進めていくことになります。
1.お客様との打ち合わせ
お客様のご要望に真摯に耳を傾け、適切な会社の設計をご提案し、会社の定款案を作成します。
2.定款の原案作成・認証
建設業許可の要件を満たすように定款案を作成しましたら、公証役場で、公証人の先生に作成した定款を認証していただきます。
3.会社設立の登記申請
提携している司法書士の先生に登記申請をお願いします。基本的には当事務所が窓口となって手続きを進めますので、お客様に余計なお手間をいただくことはありません。
4.建設業許可申請
お客様に代わって、建設業許可の担当部署に対する建設業許可申請をいたします。最初の打ち合わせの段階から、可能な範囲で、建設業許可申請に必要な書類の作成・資料の収集を進めていきます。そのため、会社設立後にスムーズに許可を取得することが可能です。
建設業許可の法人成り認可申請代行サービス
令和2年10月の制度改正により、建設業許可を持った個人事業主が代表取締役となって会社を設立した場合、事前に行政の認可を受けることによって、許可を引き継げるようになりました。
従来は、会社設立後に新規で許可を取得する必要があり、個人での許可番号を引き継ぐことはできませんでした。しかし、現在では、必要な書類を整え、適切なタイミングで手続きを行うことにより、個人事業主での許可を引き続き有効とすることが可能となっています。
この制度を使うメリットとしては、建設業許可の空白期間が生じないこと、許可番号が引き継げること、行政へ支払う手数料(9万円)が不要になることが挙げられます。ただし、必要とされる書類も多く、認可された数も少ないため、時間に余裕をもって準備することが求められます。
当事務所では、個人での許可を会社設立後も引き継がせたいとお考えの方へ、会社設立と建設業許可の法人成り認可手続きをセットでお受けしております。ご関心がある方は申請が可能かどうか検討いたしますのでどうぞご相談ください。
建設業での会社設立等サービスの料金・費用
以下ではよくあるケースについての標準的な料金についてご案内します。お見積りについては、初回相談・調査が終わった段階で正確にご提案いたします。
1.相談・調査業務
会社の制度設計について、お客様のお話を丁寧に伺い、最適なものになるようご提案させていただきます。また、建設業許可の新規取得、建設業許可の法人成り認可について、要件を満たしているかどうか確認させていただきます。
初回相談料については、事前にお振込みいただくか、当日に現金にてお支払いください。
| ケース | 標準報酬額(税込) |
|---|---|
| 初回相談・書類確認料 | 11,000円 |
2.会社設立等手続き代行サービス(司法書士報酬を含む)
| ケース | 標準報酬額 |
|---|---|
| 株式会社設立 + 建設業許可申請(新規) | 220,000円~ |
| 株式会社設立 + 建設業許可法人成り認可申請 | 220,000円~ |
建設業許可申請(新規)については、別途行政に支払う手数料(9万円)が必要です。
3.株式会社設立にかかる費用(専門家報酬を除く)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 定款の認証手数料 | 約30,000円~50,000円 |
| 定款の謄本手数料 | 約2000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 |
| 収入証紙代 | 40,000円 |
※収入証紙代については、電子定款を利用することによって節約可能です。
サービス対応エリア
当事務所の建設業会社設立等サービスの対応エリアは次のとおりです。
福島県中通り地域の市町村
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、三春町、鏡石町、矢吹町、泉崎村
その他福島県全域を対象エリアとしています。
最後に、行政書士からのメッセージ
個人事業主の皆様で、これから会社をつくろうとお考えの皆様は、事業を成長させたいという強い意欲をお持ちなのではないかと思います。私は、夢を追いかけようとする皆様の想いが達成されるよう心から願っておりますし、ぜひサポートさせていただきたいと考えております。
建設業で会社を設立し、許可も取得しようとすれば、まとまったお金が必要です。会社設立時に先のことをよく考えていないと、定款を作り直したり、登記をやり直したりと無駄な出費が発生するリスクがあります。皆様におかれましては、ぜひ建設業の手続きに精通している行政書士事務所をご利用いただければと思います。


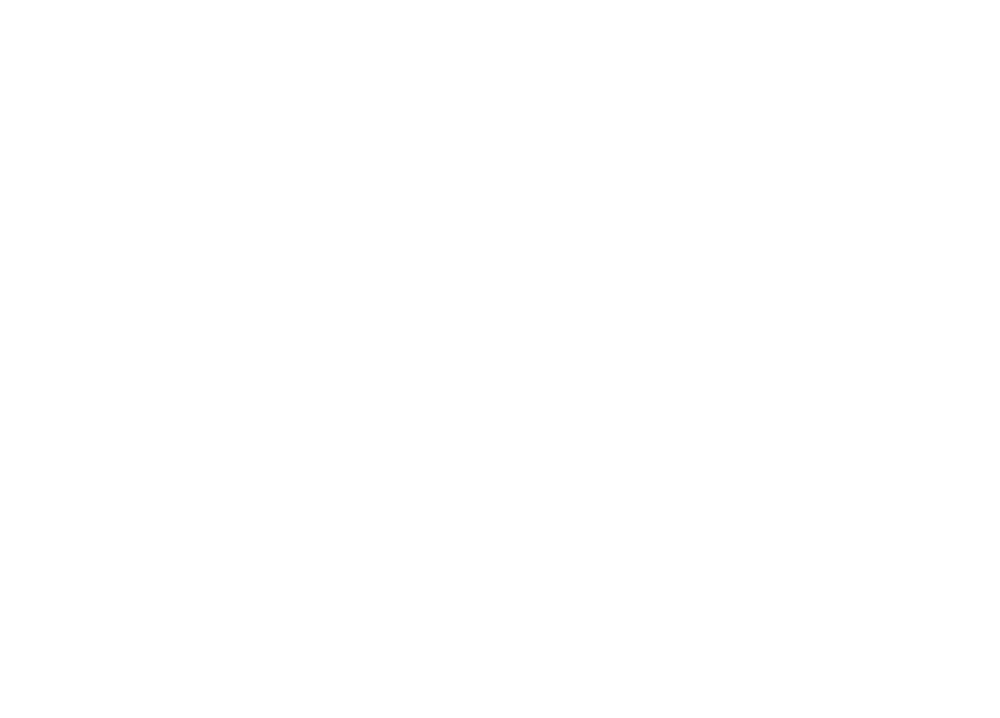


 事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。 行政書士 佐藤勇太
行政書士 佐藤勇太